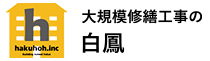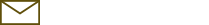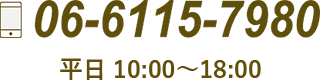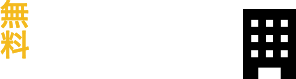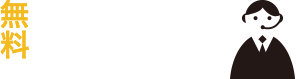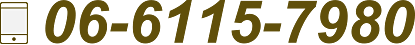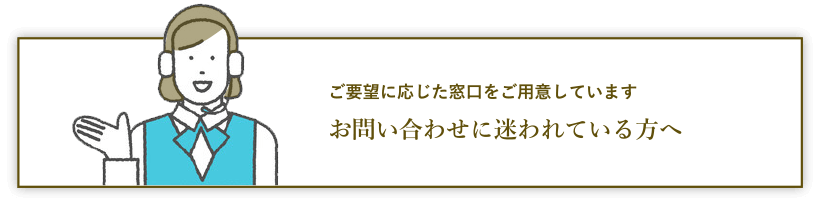12年・15年・18年?マンションにおける大規模修繕工事の周期はどれぐらい?
2024年1月12日


マンションなどの建物の安全性や資産価値を維持するために欠かせない大規模修繕工事ですが、どのぐらいの周期で行えば良いのか悩んでしまう…というオーナーの方も少なくありません。
大規模修繕の周期は、一体どれぐらいを目安にすべきなのでしょうか?
そこで今回の記事では、避けては通れない大規模修繕の周期の目安やその理由について解説していきます。
<目次>
大規模修繕を行う周期の目安は?
建物を定期的に修繕し、安全性や住環境を改善する大規模修繕工事の周期は、一般的に12年が目安だとされています。
国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」のデータを見てみても、約7割以上が12年から15年に1度の周期で大規模修繕を実施しているというデータが出ていることから、約12年程度を目安に、マンションなどの建物の構造や工法、設備内容、立地条件、劣化具合などを把握した上で個別に適切な周期を検討する必要があります。
なぜ大規模修繕は12年周期を目安とするのか
では、なぜ大規模修繕工事は、12年周期が目安となっているのでしょうか?
それには、以下のような理由があります。
12年周期の理由①:国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」の影響
大規模修繕が12年周期を目安としている理由の一つに、国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」による影響があります。
一般的に、マンションにおける大規模修繕工事は「長期修繕計画」を立ててから進行されます。「長期修繕計画」とは、マンションの管理組合の主導で作成される長期的な修繕計画で、主に、建物の劣化や損傷などの修繕を行う頻度や、どの程度の修繕を行うかを明確にするために作成されるものです。
この長期修繕計画の基本的な考え方を示すために発表されたのが、国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」です。このガイドラインには、長期修繕計画の基本的な作成方法、毎月の修繕積立金の決め方、長期修繕計画の標準フォーマットおよび作成法などが記載されています。
実は、この「長期修繕計画作成ガイドライン」の中で、外壁の塗装や屋上防水などを行う大規模修繕工事の周期が12年程度だとされているのです。
「長期修繕計画作成ガイドライン」が発表された平成20年以降、このガイドラインを参照して修繕計画を作成する会社が多くなったことで、大規模修繕は12年周期で行うというのが一般的な目安となった理由の一つとなっています。
12年周期の理由②:全面打診調査の実地時期と重なるから
大規模修繕が12年周期を目安としている理由には、全面打診調査の実地時期と重なるからというものもあります。
平成20年4月の建築基準法改正によって、定期報告制度の調査や検査基準が厳格化され、築10年以上で外壁がタイル貼りのマンションは3年以内に外壁の「全面打診調査」を実施することが義務付けられました。
「全面打診調査」とは、タイルを叩いて外壁タイルと下地の間の隙間がないかを見つける調査のこと。
外壁タイルは専用の接着剤で貼り付けられるため、経年変化によって接着剤が劣化すると、タイルの間に「浮き」と呼ばれる隙間が生じます。すぐにタイルがはがれることはありませんが、劣化が進んだ外壁タイルが落下すると、人に損害を与える大事故になりかねません。そのような重大な事故を防止するため、築10年を経過したタイル貼のマンションでは3年以内に全面打診調査が義務付けられるようになったのです。
この外壁の全面打診調査を行うには、足場を設置する必要があるのですが、足場を設置すると多くの費用がかかるため、同様に足場を用いる大規模修繕工事を同じ時期に実施することで費用を抑えようという考え方が一般的になっています。
12年周期の理由③:塗料や資材の劣化タイミングを考慮している
大規模修繕が12年周期を目安としているのには、塗料や資材の劣化タイミングに合わせて設定しているという理由もあります。
マンションに使われる塗料の寿命はおよそ8年、長持ちして12年だと言われています。
12年以上経過した塗料は、劣化によって浮き・ひび割れ・結露・欠損などが進行してしまい、建物を十分に保護することができない状態になります。その結果、建物に使われているコンクリート内部に深刻なダメージが出てしまう…ということもあり得ます。
マンションなどの建物を長く維持するためには、建物内部における劣化を予防することが大切です。そのため、塗料や資材の劣化タイミングに合わせて大規模修繕を行う目安を12年周期としていることが多いようです。
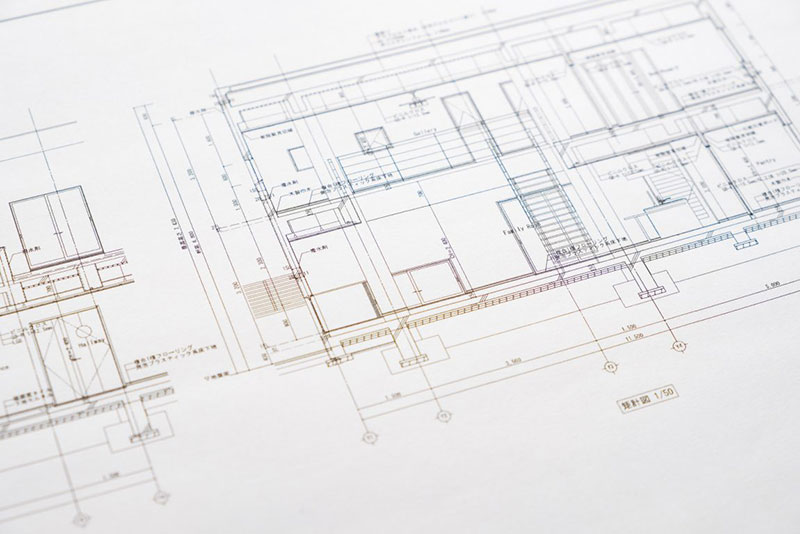
マンション部位別の修繕周期の目安とは
12年周期で行われる大規模修繕工事ですが、マンションの部位によって劣化の進み具合が異なるため、それぞれ修繕周期には以下のような部位別の目安もあります。
| 屋上 | 10年 |
| ベランダバルコニー | 12年 |
| 外壁 | 13年 |
| 廊下や階段 | 12年 |
| エントランスなど | 20年でリノベーションが理想的 |
一般的に、マンション全体の大規模修繕は12年から15年周期で行いますが、大規模修繕工事の前に、上記を参考に部位別の小規模な修繕をすることで、建物をより長持ちさせることもできます。
12年周期の大規模修繕、2回目以降はどう変わる?
12年周期で行われる大規模修繕工事ですが、2回目以降は、1回目と比べて建物の劣化の進み方が違うため、修繕工事の内容も異なってきます。
では2回目以降、大規模修繕工事の内容はどう変わるのでしょうか?
基本的に2回目の大規模修繕では、1回目と比較して修繕箇所が増える傾向があります。というのも、12年周期と考えると2回目の大規模修繕では、建築されてから少なくとも24年ほど経過しており、1回目よりも建物や設備の老朽化が進んでしまうからです。
また1回目の時に、それほど劣化が進んでいないと修繕を先送りにできていた箇所なども、2回目の大規模修繕工事では修繕対象に含まれてしまうことも少なくありません。
国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」のデータでも、1回目よりも2回目の方が外壁塗装や屋根防水のほかに、建具・金物等や共用内部などの工事金額の割合が増えていることが分かります。
マンションなどの建物は築年数に応じて劣化が進みます。そのため、大規模修繕工事は回数を重ねるごとに修繕範囲が広くなって行くことを理解し、いざ大規模修繕となった時に修繕費用が不足している…ということが起こらないようにしっかり計画しておきましょう。
関連記事:「大規模修繕工事の内容をわかりやすく解説!失敗しない進め方は」
関連記事:「大規模修繕!マンションでは何が行われる?」
15年・18年周期で大規模修繕の実施も
これまで、12年周期での実施が目安とされることが多かった大規模修繕工事ですが、近年では、15年や18年周期での修繕が提案されることもあります。
これには、一般的な目安である12年周期よりも長い周期にして工事回数を減らすことで、費用が抑えられるというメリットがあります。
例えば、60年という期間で考えると、12年周期で大規模修繕を行う場合、工事の回数は5回ですが、15年周期であれば4回、18年周期であれば3回程度となります。大規模修繕工事1回あたり数千万円から億単位で費用がかかるとすれば、マンション経営を行う上でかなり大きなコスト削減となります。
ただ、15年周期や18年周期の場合、次の修繕までの間隔が長いため、局所的な劣化によるトラブルが起こりやすくなり、結果として必要な修繕が増えてしまう場合があります。大規模修繕工事を15年や18年周期で行う場合には、建物診断を受けた上で綿密な修繕計画を立てておくことが重要です。
もちろん環境や条件によっては、18年周期よりも12年周期がいい場合や、逆に18年周期の方が合っている場合もあるため、まずは外壁診断とシミュレーションで確認したり、あらかじめ信頼できる施工業者に相談しておくなどで対応しましょう。
関連記事:「大規模修繕の費用はいくら?工事費用の相場や足りない場合の対処法について解説」
マンションの大規模修繕なら白鳳にご相談を!

今回は、大規模修繕工事の周期について解説いたしました。
マンションにおける大規模修繕工事については、建物が建造された状況や周辺環境などによってもベストな周期が変わってきます。大規模修繕を行う際にはあらかじめ建物診断をしっかり行った上で修繕の計画を立てることが大切です。そのためには、アフターケアまで考えてくれる信頼できる業者を選ぶことが大切です。
マンションは建て替えまでに数十年という期間があります。その間複数回にわたって修繕が必要になるため、長期的なスパンでケアを考えてくれる優良業者に依頼することが、マンションを長く安全に保つことにつながります。
私たち白鳳は、お客様のご希望に寄り添った大規模修繕工事を実現します。ご相談は無料となっておりますので、大規模修繕でお悩みのマンションオーナー様はぜひ一度お問い合わせください。